- 体調が悪いとき(再燃期)は、どんな食品に気をつけたらよいの?
- なぜ、食事に気をつけるの?

というあなたへ
こんにちは
看護師のたかはしです
ナース歴・潰瘍性大腸炎歴はともに20年以上となりました。
あなたの症状が少しでも改善されますよう、これまでの苦労や経験を活かし、医療者としてご提案・ご案内をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします!

潰瘍性大腸炎の人も・そうでない人も、体調が悪いときの「食事の気をつけかた」は基本同じです。
胃腸に負担をかけない食品選びをして・調理法や食べ方に配慮する・というシンプルなものなんですね。
ただですね、例えば寛解期に食べてよいものが、再燃期ではNGだったり、同じ潰瘍性大腸炎の人にすすめられた食品や、栄養指導で受けた一般的に良い食品が自分に合わない場合もあったりして、少々混乱を引き起こしています。
結局、何を食べたらいいのか・わからない…。

「その食品が自分の体に合うか・合わないか」という点は、食事療法以前に大切なポイントではあるのですが、潰瘍性大腸炎だからといって、特別にこれを食べましょう!ということもありません。
あなたにお伝えしたいことは、「潰瘍性大腸炎の再燃期の腸」がどんなふうになっているかです。
再燃期の「腸」の様子がわかれば、食事に気をつける理由・どんな食品がNGなのかを理解しやすくなりますので、ぜひ最後までご一読くださいね。

腸の様子も体質も人それぞれですよ。
再燃期・食事に気をつける理由
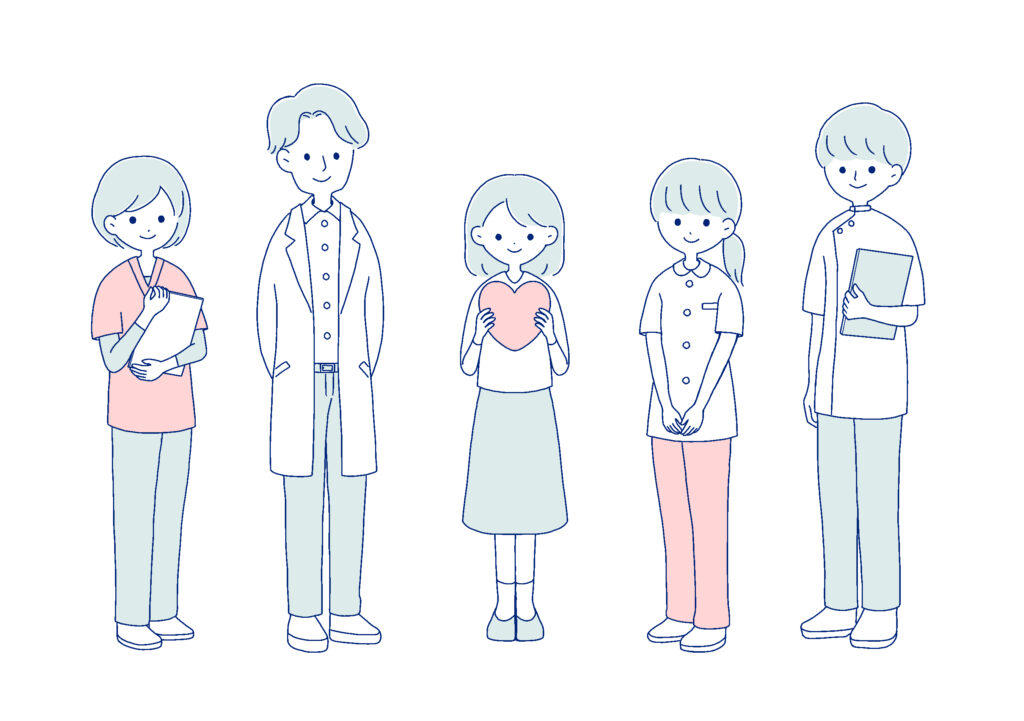

なぜ気をつけるのか、しっかり抑えましょう
潰瘍性大腸炎・どんな病気?
潰瘍性大腸炎は何らかの理由で、本来自分を守るはずの免疫システムが暴走し、自分の腸を攻撃するんですね。
攻撃を受けた腸は、炎症によりやけどを負ったような状態になります。
炎症を「火事」と例えるなら、潰瘍性大腸炎の発症・再燃は「ボヤ騒ぎ」、活動期や重症が「大火事」です。
ボヤ騒ぎでは「ただれや出血」を、大火事では「むくみと・狭窄」をおこします。

やけどを負った場所が「手のひら」ならば目に見えるので、治療をしたり・生活の中で刺激から守ろうとしますが、「腸」は体の中なので何がどうなっているかわかりにくく、手立てが遅れます。
やけどでめくれた皮膚や粘膜、・ヒリヒリと痛み出血してる場所に、二次被害が生じるような刺激物や負担になるものを届けてはいけません。
また、腸は一本の通り道なので、腫れて狭窄すると食べものは行く手をはばまれ、ひどければ通過できなくなるんですね。
食事に配慮する理由は、おもにそういったところにあります。
胃腸への負担
大腸は「栄養の吸収」と「便づくり」が主な仕事、胃はおもに「食べ物の消化」を行います。
体調が悪いときは、大腸をふくめて全身の機能が落ちますので、体調のよいときの生活を維持しようとすると、からだに負担をかけます。
そのため大腸だけでなく、「胃」にやさしい食事に切りかえたり、こころと体を休まる必要があるんですね。
胃腸が弱っている時は、下記のような消化の悪いもの控えます。
- 脂っこい食べ物(脂質は消化に時間がかかる)
- 刺激の強い食べ物((刺激の強いものは胃酸を多く分泌、胃の粘膜にダメージを与える)
- 食物繊維が豊富な食べ物(溶けずに腸まで届く不溶性食物繊維に注意)
食事量や、食べ方、食事の形態にも注意が必要です。
潰瘍性大腸炎だから特別にこの食事を!ということではなく、「低脂肪」「低残渣」「低刺激」を心がければ、胃腸に負担をかけません。
気をつけること・重要なポイント

食品が自分の体に合うか・合わないか
食品を除外するポイント
体調の良いとき・悪いときに関係なく、一般のかたもお腹に合わない食品は避けます。
食品を食べてみて、お腹がゴロゴロする・張る・痛む・下痢などがあれば、それは経験として「自分に合わないリスト」にあげてください。
私は、お腹の症状以外で「食べた後、舌や口の中がヒリヒリする・痛がゆい・腫れっぽい、口内炎ができた。節々が軽く痛む、熱はないけど熱っぽい・頭痛が続く」などの症状が出たときは、食事を振り返り思い当たる食品を除外してきました。
現れる症状は個人差があると思いますが、私の場合、再燃に先立ち上記のような症状が現れると認識したんですね。
一方ですぐに除外せず、ストレスや疲れのためだったかな?と原因を考えたり、調理法を変えてみる、よく噛んでゆっくり食べる・温めてみるなどして再度挑戦することもあります。
それでも毎回同じ症状がでるときは除外しています。

食品に対しての反応は、育った環境や、食習慣、調理法・それぞれの体質、持病の有無、病気の程度や範囲、腸の様子・免疫・腸内環境・日々の体調などにより左右されます。
食事や日々の体調を記録しておくと、再燃を早期に気づける可能性がありますよ。
「一般的に良いとされる食品」が自分に合わないとき混乱が起きますが、重要なことは一般例の中で自分にどの食品が合い・合わないのかをしっかりと見極めることです。
再燃期(体調が悪い時)に控える食品例

下記を参考に、どんな調理メニュー・食品が考えられるか見ていきましょう。
- 脂っこい食べ物
- 刺激の強い食べ物
- 食物繊維が豊富な食べ物
脂っこい食べ物(高脂肪)
脂っこい食べ物は、消化に時間がかかるため胃腸に負担です。

この時期は、料理に使う油は少なくするか・やめましょうね。
調理
こってり料理全般・洋食・中華・肉料理・揚げもの・炒めものメニュー
食品例
脂身の多い肉(牛肉・豚肉・皮つき鶏肉・レバー)・加工食品(ベーコン・ウインナー・ハムなど)・牛乳(低脂肪除く)・クリーム・アイス・チョコレート・ケーキ・洋菓子・菓子パン・フライドポテト・ナゲット・ピザ・スナック菓子・カップ麺・マーガリン・バター・油類・マヨネーズ・チーズ・ナッツ類など
刺激の強い食べもの
刺激の強い食べものは、胃酸を分泌して胃の粘膜にダメージを与えます。また、胃腸が弱っている時は、辛みを感じやすくなるため、少しの刺激でも反応するんですね。

夏バテに良いとされる食品も、この時期は控えます。
調理
スパイスをきかせたもの・辛い中華料理・メキシカン・ある種のイタリアンなど。熱すぎる・冷たすぎる・味が濃すぎるもの(甘すぎ・苦すぎ・辛すぎ・塩からすぎなど)
食品例
わさび・からし・カレー粉・酢・かんきつ類など酸味の強いもの・コショウ・七味・シナモン・とうがらし・香味野菜・ショウガ・ニンニク・その他スパイス・アルコール・炭酸飲料・カフェインなど
不溶性食物繊維が豊富な食べ物
不溶性食物繊維は消化されず、大腸まで届きます。残渣が多いということですね。

便づくりに必要な栄養素ですが、腸に狭窄があると通過困難になります。その時は医師の指示に従いましょう。
また、消化液や消化管ホルモンの分泌を促す作用があるので、控えたほうが腸管の安静を保てます。裏ごしをしたり、繊維を細かく断てば摂取できますが、大量に摂ると下痢や張りの原因になるので、この時期は無理をせず控えましょう。
食品例
こんにゃく・しらたき・かんぴょう・もやし・セロリ・たけのこ・ごぼう・レンコン・オクラ・さやえんどう・にら・山菜・海藻・パイナップル・柿・なし・サクランボ・ブドウ・かんきつ類皮・トマトやナスの皮・きのこ類・切り干し大根・たくあん・豆類・玄米・麦・ふすま・粒あんや豆の入った和菓子・豆菓子・ナッツ類・レーズン・プルーン・とうもろこし・ポップコーンなど
その他・腸に影響があるもの
どんなふうに調理をしても繊維や形が残るものや、噛み切れないもの、生もの、砂糖漬けになったものを控えて下さい。

焦げた食品も注意です
食品例
焦げたもの・蒸しても加圧しても硬い食品全般・生のくだもの皮・完熟していない果物野菜・イカ・海老・小エビ・タコ・ムニムニして噛み切れない貝類・やわらかく調理していない食品・漬物・ピクルス・ザワークラウト・筋の多い肉・生あるいは未加工の野菜・食品添加物や砂糖の摂りすぎ・ブドウ・メロン・ドライフルーツ・ベリー・いちごやキウイなどの小さい種・くん製品・スルメイカ・つくだ煮・塩辛・ココアなど

上記の食品例は、直接「腸」を刺激するもの、腸内で発酵が強まるもの、腸内環境の乱れの原因になるものが含まれていますよ。

ぜひ参考にしてくださいね
まとめ


いかがでしたでしょうか。
再燃期(体調の悪いとき)の腸は、下記のような状態になります。
- 炎症を伴ない表面がただれる(痛々しい状態)
- 態により出血・下痢・痛みがあらわれる
- ひどければ腸がむくみ狭窄する(便の通り道が細くなる)

食事で気をつけることは、風邪や胃腸炎と基本おなじですが、病態でみると潰瘍性大腸炎は重い病気ですので、その違いはしっかりと抑えてくださいね。

またお腹に合うもの・合わないものを日頃から把握しておきましょう。
下記は、再燃期(体調の悪いとき)に控える食品の特徴です。当てはまる食品に気をつけましょう。
- 脂っこい食べ物
- 刺激の強い食べ物
- 食物繊維が豊富な食べ物

それではこのへんで、今日もありがとうございました。

お体ご自愛下さいね
下記の記事は、再燃期・症状が悪化したときの食事についてです。症状改善を目指す手がかりになれば幸いです。ぜひご覧ください。

